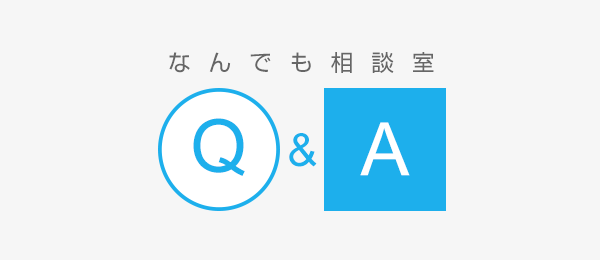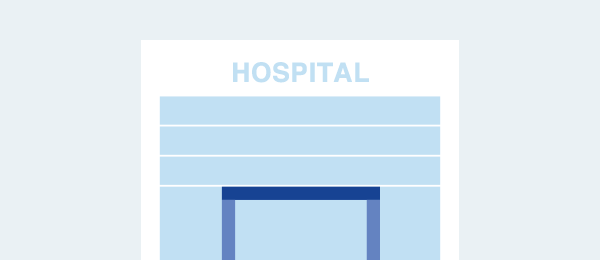クローズup PDホスピタル
腹膜透析の情報誌「スマイル」
愛知県 医療法人豊田会 刈谷豊田東病院
記事の内容、執筆者の所属等は発行当時のままです。
患者さんの治療への参画を支援する体制を構築
同院の母体である総合病院では、患者さんに積極的に治療へ参画していただき、患者さんの思いを医療につなげていくことを基本方針に挙げ、腎疾患・透析治療を行っています。
患者さんの治療への参画を支援するために総合病院が作成したのが「慢性腎臓病(CKD)ロードマップ」。CKDと診断された保存期患者さんは、この「ロードマップ」で自分の病気がどの段階にあり、今後治療がどのように進むのかを把握できるようになっています。そして、個々の患者さんに合わせた教育を行っているのが「透析予防外来」です。「透析予防外来では、1人1人の患者さんに合わせた個別指導を行っています。医師だけでなく、看護師、薬剤師、栄養士が連携して、1回約2時間の情報提供と教育を実施し、患者さんの自己管理能力を高め、自立した生活を送れるようお手伝いしています。透析を導入したとしても、腎臓の機能を100%補えるわけではありません。透析の力を借りながら、健康的な生活を送るために、『自分の腎臓は自分で守る』という意識を持って治療に参画してもらうことが必要です。そのためにも患者さんに進んで勉強してもらえる体制を構築しています」と話すのは腎臓内科部長の小山勝志先生。
一方、同院では透析導入後の患者教育にも力を入れており、HDを選択した患者さんに対しても地域の透析クリニックで治療を開始する前に、同院外来で1~2カ月間自己管理を学んでもらい、透析人生のQOL向上につなげています。
PDを選択してもらう、そして、PD治療の質を保つ
病状が進行し、腎代替療法が必要となる患者さんには、「療法選択外来」で、ライフスタイルや疾患の状態に合わせた治療に関する情報提供を行います。「残存腎機能がある患者さんにとって、PDはメリットが大きい治療だと考えていますので、積極的にPDを勧めています。PDは自分で治療を行うため敷居が高いと感じる患者さんは多いのですが、看護師からPD導入後の生活や訪問看護の説明をしてもらうなど、PDを選ぶことができる体制をつくっています」(小山先生)。
PD診療においては、治療の質を保つためにさまざまな取り組みを行っています。まず、PDの導入を担当した医師が導入後も引き続きその患者さんの主治医を務めます。導入だけでなく経過も診療し続けることで医師はPDに精通しますし、学会発表などを積極的に行うことでPD診療の質の維持や普及にも尽力しています。
また、3人のPDナースが中心となってPD診療を行っている点も同院の特徴です。PDナースは問診で患者さんの情報を収集するだけでなく、患者さんの生活や意向に鑑み、治療方針について医師に提案も行います。「最終判断は医師が行いますが、患者さんの生活や状態を把握しているPDナースからの提案は重要です。また、患者さんの悩みにアドバイスをしたり、患者さんごとに自己管理能力の判定をして継続的な教育をしたりと、PDナースは大きな役割を果たしてくれています」(小山先生)。
さらに、より効率的で質の高いPD診療を目指し、APD(自動腹膜透析)の遠隔管理について、臨床工学技士との協力体制の構築を計画しています。また、高齢患者さんが増えることを想定して、訪問看護ステーションとの連携強化や、導入後の手技習得が不安な方のための教育入院制度の検討など、PD患者さんを支えるさらなる仕組みづくりを進めています。
最後に、小山先生から「PDには残存腎機能を保ちながら透析ができるという大きなメリットがある一方で、患者さん自身が毎日治療を行う大変さが伴うことは医療者側も認識しています。苦しいときは私たちにどんどん相談してください。一緒に頑張っていきましょう」というメッセージをいただきました。