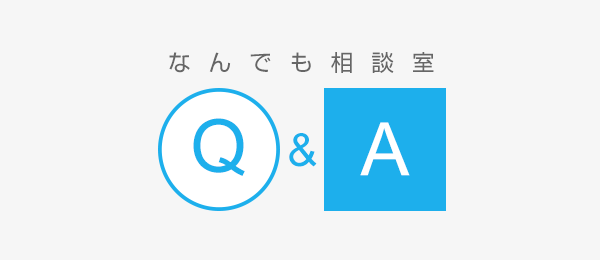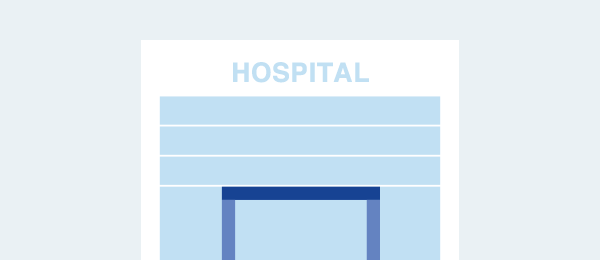クローズup PDホスピタル
腹膜透析の情報誌「スマイル」
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター
記事の内容、執筆者の所属等は発行当時のままです。
SDMの考えに基づき段階を踏んで腎代替療法について説明
「当科では、医療者と患者さんが互いに情報を共有して一緒に治療を決める“Shared Decision Making(SDM)”の考えに基づいて治療を行っており、エビデンスと患者さんの希望の双方を大事にしています。また、医師だけでなくメディカルスタッフと協力して、60人を超える全国でも有数のPD患者さんの診療に当たっています」と話すのは腎臓内科教授の森下義幸先生。
腎代替療法の選択に際しては患者さんの気持ちを第一に考え、段階を踏みながら説明する体制を整えています。まず透析部看護師が1時間ほどかけて患者さんとご家族に血液透析(HD)、PD、移植に関する説明を行いながら、患者さんから生活の状況や趣味などについて話を聞いた後、医師と看護師が同席する術前外来でそれぞれの治療法の具体的なイメージを持ってもらえるよう追加の説明をします。同科の北野泰佑先生は「メリット・デメリットを含めさまざまな情報を伝えた上で治療法を選んでいただきますが、この時点で決められない場合もあります。その際は再び看護師と相談する時間を設けるなど、納得されるまで時間をかけるようにしています」と話します。また、同科の平田桃子先生は「透析と聞くと、マイナスのイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、PDはHDに至るまでの時間が延長できる上に、時間を有効に活用して自分らしい人生を送ることが可能な治療ですので、選択肢として考えてもらえるよう説明しています」と言います。こうした段階を踏まえた説明は、同センターで腎代替療法を導入するほぼ全ての患者さんに行われています。
月ごとにテーマを決めて行う看護師による患者指導
個々の患者さんに適した治療を提供するという方針は、療法選択時だけではありません。「原疾患や残存腎機能の状態、合併症の有無、生活背景など、患者さんの状態は多様です。PDでは、APDを使うかどうか、残存腎機能が落ちてきたときにHD併用をするか否かは人それぞれです。また、チューブの固定方法も生活する中で当初指導したやり方と違ってしまっても、出口部の状態に問題がなければその方法を取り入れるなど、患者さんの状況を確認してチームで共有しながら、それぞれの患者さんに合わせた対応を行っています」と北野先生。
また、看護師の関わりもPD治療を支える大きな力となっています。PD患者さんの定期外来時には、看護師が問診、出口部の観察を担当しています。加えて、患者さんの知識が自己流にならないよう月ごとにテーマを決め、指導を行っています。透析部看護師の小野瑞紀さんは、「出口部の感染対策、バッグ交換の手技、お風呂の入り方や災害時の注意点など、内容は多岐にわたります。今月はPDを長く続けるために残存腎機能を保つにはどうしたらよいかをテーマにしました。腹膜の劣化を防ぐ生活のコツやHD併用のメリットについても触れています。患者さんにお渡しする資料も私たち看護師の手づくりです」と話します。
コロナ流行下での治療については、PDは通院回数が少ないという大きなメリットがある一方、引きこもりがちにならないよう声かけを行っていると教えてくださいました。
最後に、森下先生からは「PDは高齢者にも向いている治療です。やってよかったという高齢者の方もたくさんいらっしゃいます」、平田先生からは「自宅で行うPDは不安な面も多いと思いますが、私たちスタッフが全力でお手伝いさせていただきます」、北野先生からは「感染症の合併や排液がうまくいかないなどトラブルに遭遇することはあるかもしれませんが、安心して続けられるようサポート体制を整えていますので心配しないでください」、小野さんからは「PDを長く続けていくためになんでも相談してください。一緒に頑張っていきましょう」というメッセージをいただきました。