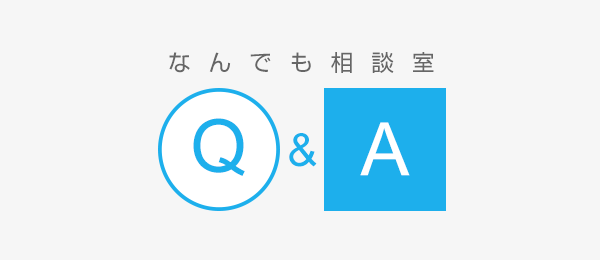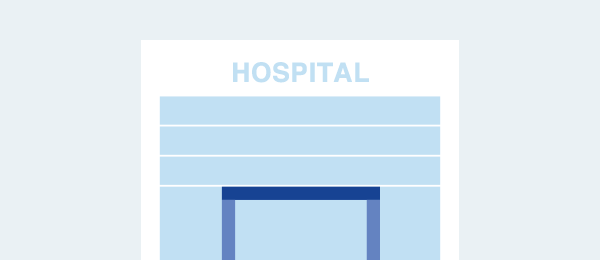クローズup PDホスピタル
腹膜透析の情報誌「スマイル」
東京都 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院
記事の内容、執筆者の所属等は発行当時のままです。
人生設計に沿った腎代替療法選択を支援
「腎臓内科では窮民救済の考えに基づき『患者さんの笑顔のために頑張ろう』をスローガンに診療を行っています」と話すのは副院長の竜崎崇和先生。患者さんの教育・啓発にも積極的に取り組んでいます。「腎臓病の教育入院に加え、70人規模の腎臓病教室を年2回開催し、患者さんへの啓発活動を実施しています。また、当院は糖尿病診療に力を入れており、糖尿病患者さんが多いので、糖尿病教育入院時にも、腎不全や腎代替療法のレクチャーの時間を設けています」。
外来の待合スペースでは啓発用のDVDを流したり、冊子やポスターを掲示したりと保存期の患者さんが腎代替療法に触れる機会もつくっています。治療の決定に当たっては、「腎代替療法選択支援外来」を開設し、月20人ほどの方が受診しています。「治療について、偏ることなく、また例を挙げて分かりやく伝えるようにしていますが、一方的な説明に終始せず、まずは患者さんから話をしてもらえるように心がけています」と、透析室師長の宇賀神ゆかりさんは話します。「患者さんの人生設計の中で、どの時点でどんな活動をしたいかを考えてもらいます。条件が整うようであれば移植を提案しますし、PDは時間的な制約が少ない上に、今は新型コロナウイルスへの感染機会を減らす点でも優れていることを伝えています」と竜崎先生。「医師と看護師で常に情報を共有しながら、個々の患者さんにとってどの治療が最善かを考えています」と腎臓内科副医長の小松素明先生が話す通り、チームで療法決定を支援しています。また、同院では保存期から透析に至るまで同じ医師や看護師が患者さんと関わっており、一貫したケアが可能になっています。
さまざまな取り組みで「治療の質」向上を目指す
PD診療において、常に「治療の質」向上に取り組んでいる同院。例えば、出口部感染に対しては、患者さんの生活を考慮して看護師が出口部の位置について医師と相談したり、外来時に毎回出口部の写真を撮って評価したり、ケアの方法を個々の患者さんに合わせて調整するなどした結果、発生数が減少しました。また、カテーテル留置術は腎臓内科の医師が行っており、出口部の位置の柔軟な対応やカテーテルがはねない工夫を行っています。
合併症管理の一環としては、誕生月に透析患者さんに対し心血管病検査(バースデー検査)を実施しています。小松先生は「腎不全の患者さんは全身の管理が重要です。骨密度や足関節上腕血圧比(ABI)などを計測し、腎臓だけでなく周辺疾患に対しても丁寧な診療に努めています。最近では重症下肢虚血に至る患者さんが多く、循環器内科、血管外科、形成外科、皮膚科などがチームを組み血管内治療に当たっています」と話します。
また、日本腹膜透析医学会(JSPD)教育認定施設として、多くの病院から研修を受け入れています。「外来や手術など実際の現場を見学してもらいます。われわれも他施設で行っている取り組みを知りたいと考えていますので、まずは一緒にディスカッションするところから始めています」と竜崎先生。宇賀神さんは「現場ですぐに実践できることを紹介し、使用している用紙や説明書なども提供しています」と言います。
最後にPD患者さんに向けて、宇賀神さんからは「退院前訪問で自宅の環境を整えるサポートをしていますが、さらに充実させたいです。自分の生活の一部になるようPDを上手に組み込んで、患者さんらしく楽しく過ごしてほしいです」、小松先生からは「PDは“元気に食べて元気に生きる”治療法です。これから治療が必要となる方には透析を拒絶せず、心を開いてもらえればうれしいです」、竜崎先生からは「PDは残腎機能や生活のリズムに合わせて治療が設定でき、患者さんのやりたいことを優先できる治療です。今年のJSPD学術集会を大会長として開催します。日本のPDの将来に向けて多くの医療者とともに考えていきたいと思います」とのメッセージをいただきました。