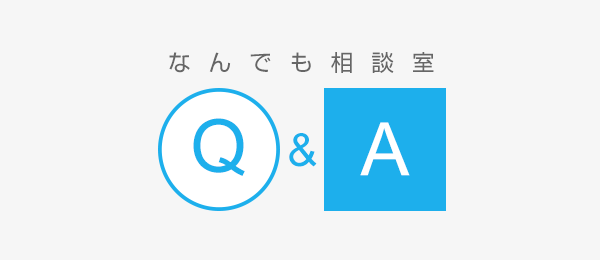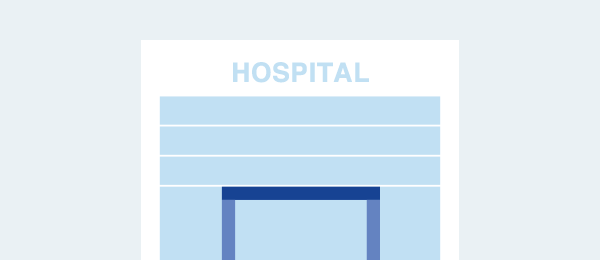クローズup PDホスピタル
腹膜透析の情報誌「スマイル」
栃木県 日本赤十字社 足利赤十字病院
記事の内容、執筆者の所属等は発行当時のままです。
多職種による腎臓病チームを編成し、腎臓病治療を担う
同院の腎臓内科・透析センターでは、医師5人、看護師18人に加え、臨床工学技士、薬剤師、栄養士、リハビリテーション科の多職種から成るチームを編成し、腎臓病患者さんの治療に当たっています。腎臓病を的確に診断し、進行・悪化を食い止め、透析療法へと進行する患者さんを減らすことを基本方針として日々努力しており、地域の医療機関に向けた講演会を開催するなど、地域全体で患者さんを診る体制の構築にも注力しています。
同院の副院長で腎臓内科部長・透析センター長の平野景太先生は「地域の診療所からの紹介で多くの患者さんが受診されます。診療所が主体となる診療をサポートする形で、当院で腎臓専門医による診察と多職種による服薬指導、栄養指導や療法選択指導を行います。もし、腎代替療法が必要となった場合は、患者さんを全面的にお引き受けし、できるだけ生活に不利益が少なくなるよう多様な治療の提供にチームで対応しています」と説明します。
同院で透析を導入する患者さんは年間約90人。現在は保存期約200人、血液透析(HD)70人、腹膜透析(PD)65人、HD / PD併用10人の診療に当たり、腎移植への橋渡しも年間5人ほど行っています。
透析患者さんの生活に寄り添う看護師が療法説明を担当
腎代替療法の選択に際しては、腎臓病チームの看護師が内科外来に足を運び、患者さんやご家族が理解できるように4~5回にわたって面談を行っています。「実際にHD・PD患者さんと日々関わり、生活や悩みを知る看護師が療法選択指導を行います。特定の治療に偏ることなく、多くの患者さんの生活に寄り添うことで得られた経験や知識が、患者さんへと還元されていく、こうした循環が重要と考えています。また腎臓病チームで勉強会を開き、スタッフ間の知識、技術の標準化に努めるとともに、電子カルテで患者さんの生活状況や思いなどを共有し、特定の看護師だけでなく、全員で療法選択に関わっています」(平野先生)。
同院の555床ある病室は全て個室となっており、他の患者さんを気にすることなく個々の患者さんの背景や生活の様子、病気の状態、希望する治療法、今後目指したい社会復帰のレベル、合併症や予後について、患者さんと医療者が話し合うことができます。プライバシーが守られた空間での話し合いは、多様な治療選択にもつながっています。

治療成績を共有し、適切な指導につなげる
「患者さんに『この治療を選んで良かった』と思ってもらえることが重要」と話す平野先生。同院では、透析室のスタッフが頻繁に行き来する場所に、HD・PDの治療成績データが掲示されています。日本透析医学会による日本の平均PD継続期間と同院のデータを比較して、全国平均を下回ることがないようスタッフの意識を高めるなど、治療成績を共有することで適切な指導につなげています。
写真:平野先生と病棟スタッフの皆さん
また、高齢で通院が困難になってしまった患者さんには訪問診療で対応する病診連携の充実を図るなど、さまざまなライフステージの患者さんやご家族の支援体制を整えています。
最後に平野先生から「PDにもHDにもそれぞれの良さがあり、欠点があります。PDは心臓への負荷が少ない可能性があり、通院回数が少ないため豊かな社会生活を送ることができるというメリットがあります。当院は多くの患者さんを診てきた経験から、その良さを生かして社会復帰を支援するノウハウが豊富ですので、いつでもご相談にいらしてください。お孫さんの世話、仕事、山登り、散歩をしたいなど、それぞれがに望む社会復帰の内容は異なります。自分が考える社会復帰のレベルにたどり着けるように治療していきましょう」とのメッセージをいただきました。