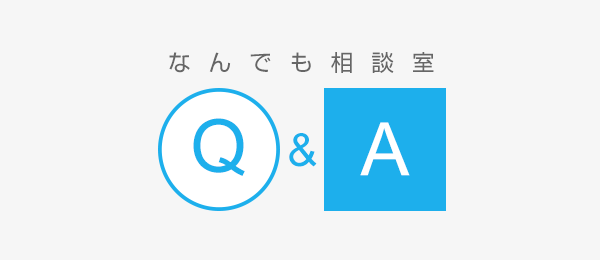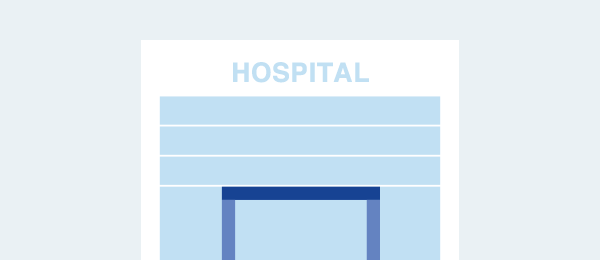クローズup PDホスピタル
腹膜透析の情報誌「スマイル」
大分県 大分県厚生連 鶴見病院
記事の内容、執筆者の所属等は発行当時のままです。
透析導入を少しでも遅らせるためにさまざまな取り組みを実施
同院では、1991年に透析治療を始め、1994年からは腹膜透析(PD)治療を開始しました。PDと血液透析(HD)の併用療法も早くから取り入れ、個々の患者さんの状態に応じた治療を提供し、現在はHD約90 人、PD約60 人(うち併用20 人)の患者さんが通院しています。
「慢性腎臓病(CKD)の治療に当たっては、透析導入を少しでも遅らせることを目指し、『腎臓病教室』を約20年間にわたり開催しています。また、院内の多職種で連携を図る『CKDカンファレンス』、個々の患者さんの状況に合わせて対応する『CKD外来』などに加え、自治体や医師会などと『別府・ゆけむりCKDネット』を構築し、開業医の先生方との連携や地域の患者さんへの啓発活動にも取り組んでいます」と腎臓病センター長の安森亮吉先生は話します。
CKD外来により透析導入も前向きな気持ちで
同院でCKD外来が始まったのは2014年。腎臓病の進行を抑えるための取り組みとして始まり、人工透析センターの看護師4人が交代で担当しています。
そのうちのお1人、看護師の清水郁子さんは「CKD外来は、近い将来に透析導入が見込まれる患者さんにとっては、治療に納得して前向きに取り組んでもらうための機会でもあります。患者さんの思いを聞いて受け止めること、理解や気持ちの受け入れの程度を確かめながら説明することを心がけています」と語ります。「CKD外来で情報や知識を得ることによって心構えができ、実際に透析導入となったときに、『透析は嫌』ではなく、『透析を始めたらどう過ごそう』と、前向きに考える患者さんが増えてきたように感じます」と人工透析センター長の有馬誠先生。
ただし、透析導入の約半数を占める他の医療機関から紹介されてきた患者さんの場合には、導入までの時間が限られCKD外来での説明ができないこともあります。有馬先生は「そういった患者さんにもできる限り病棟で説明をして、その方に合った治療を提供できるようにしています。緊急導入に近い状況でもPDを選ぶ方がいるのは、当院にはPD患者さんが多く、実際の患者さんを目にする機会があることも一因かもしれません」と話します。
家族のサポートなしでもPDを行えるように
今年度、同院が特に力を入れているのが、在宅での「継続看護」に関する取り組みです。学習会を介して地域の訪問看護ステーションや医療機関と連携を図り、さまざまな状況にある患者さんが自宅でPDを行える仕組み作りを模索しています。「当院では、残存腎機能保持の観点から、PDファーストを基本としていますが、高齢で独居の方や家族が働いている患者さんも増えています。家族のサポートがないからPDを導入できない、続けられないというのは残念なことですので、訪問看護ステーションなどにPDを理解してもらい、連携していきたいと考えています」と4階病棟看護師長の西川幸子さんは語ります。「家族の支援が得られても、家族が疲弊してしまうのは避けなければなりません」と有馬先生、「PDは高齢者にこそ向いている治療と考えますので、大切な取り組みだと思います」と安森先生もその重要性を強調します。
最後に患者さんへ向けて、「PDは自分なりのスタイルに合わせた治療が可能です。あまり肩肘張らずに自分を信じて生活していきましょう」(有馬先生)、「できないところはフォローしますから、安心して受け入れてください。心配はいりませんよ」(西川さん)、「日々、規則正しい生活を続けましょう」(安森先生)、「透析開始時に車椅子だった方でも、今はお化粧をして杖を持って歩いている方もいます。治療で元気になれますので、せっかくの命、どう生きたいか考えてみてほしいですね」(清水さん)というすてきなメッセージをいただきました。